名前は有名ですが、海坊主はどんなことをする妖怪なのかはっきり答えられる方は少ないのではないでしょうか。
海坊主には、海入道・海法師・海小僧・海難法師・海座頭などの別名があります。
なぜか全て仏教のお寺にいる僧の役職名になっているのが不思議ですね。
月末に漁に出たり、夜に釣り船を出したときの遭遇譚が多いようです。
江戸時代までの日本は太陰暦(月の周期にあわせた暦)を使っていたため、月末の日はほぼ必ず新月になります。
月明かりがなく暗くなる日の夜に船を出すのは危険だといういましめかもしれません。
大まかに海坊主といえば、海面にいきなり上がってきてびっくりさせたり、急に船をひっくり返したりするものが多いようです。
サイズはまちまちですが、大きいものは2メートルにもなるといわれます。
よく船を出している漁師でも、めったに鯨が現れない地域の人なら、鯨が水面に上がってきたのに驚くことがあるかもしれません。
しかし、鯨漁が古くから盛んな和歌山県沖などでも海坊主と呼ばれるタイプの妖怪の言い伝えがあります。
夜の砂浜に出没して、相撲を仕掛けてくる海坊主もいます。
相撲は古代から神事のはずなのも興味深く、四股を踏んだりすると邪気が祓われるとされています。
しかし海坊主との相撲はその後体調を崩したり亡くなってしまうと言われ、悪いことを呼んでしまう相撲ということになります。
また海で取れる塩も清め・祓いの性質を持っているはずのアイテムで、なぜこのように悪意のある妖怪がわざわざ海で神事を汚すのかはよくわかっていません。
夜の海に気軽に出かけるなといういましめにしても、少し疑問が残りますね。

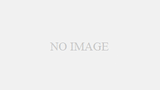
コメント