有名な民俗学者である柳田國男氏が残した遠野物語という書籍は、カッパとザシキワラシに関する記述が有名です。
遠野物語は昔話を集めたものですが、柳田氏が取材した東北にはカッパの目撃談が数多く残っていたといわれています。
カッパを漢字で書くと河童になりますが、このままカワワロカワワッパと呼んでいた地域もあります。
カッパという呼び方が定着したのは、上記の柳田氏と水木しげる氏が広めたこともあるかもしれませんね。
和歌山の紀ノ川流域ではガアタロ(川太郎)と呼ばれていたり、エンコ・セコ・メドチ・シバテンなどと呼んでいた地域もあるようです。
お住まいの地域のカッパの呼び名を調べて見ると、特別に固有名詞がついたカッパの言い伝えが見つかる場合もあります。
ネネコガッパやクセンボウ、ケンヒキ太郎など、その地域で人間と交流したことのあるカッパだけが名前を伝えられています。
あるお城を作る際にわら人形に命を吹き込んだものが放流され、それが後々カッパになったという話が福岡に伝わっているそうです。
昔は山の中で生きている民など、身分のない人は重労働であってもお仕事を任されることがなく、そうした人たちに仮の身分を授けたという話がこうして伝わっているかもしれませんね。
アニメのまんが日本昔話で、人間になりたくて雨乞いを手伝ったカッパの話が放送されたことがありますが、これがどこの民話なのか、それとも創作なのかは定かではありません。
腕を切られて奪われたカッパが腕と引き換えによく効く傷薬を伝えたとか、捕らえられて逃がしてやる代わりに魚をたくさん取れるようにしたとか、少なくとも人間と会話ができる存在であったことは多いようです。

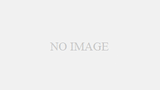
コメント