海に出没する妖怪といえば何を思い浮かべるでしょうか。
海坊主や海入道と呼ばれる、ぬるぬるしたよくわからない妖怪は有名です。
夜に出てくるらしく姿がはっきりしません。
遭遇した人は相撲を挑まれたりして、翌日や三日後などに亡くなってしまうといわれています。
古事記の時代から、荒れた海を鎮めたり、思うように船が進まなくなってしまったときには人身御供(いけにえ)を海にささげる風習があったことからも、海は人が死ぬところなのだというイメージは強いと思います。
海の妖怪でもっとも特徴的なのが、夜に出てくるものは出会うと死んでしまったり、漁業の最中に遭うと魚が取れないか大漁になるかの両極端だったりします。
妖怪のウミガメに遭遇したときは不漁といわれる地域や、大漁といわれる地域が分かれます。
実際の海亀は魚の群れを追いかけることがありますが、代わりに海亀を良く食べる鮫をおびき寄せてしまうこともあるため、鮫の多い地域では海亀を見たら早めに帰港するのが良いのかもしれないですね。
沖縄や奄美などでも、ガジュマルという樹の妖精キジムナーや、正体不明のケンムンという妖怪が漁の出来を左右します。
魚が取れなかったときの言い訳や、期待していなかったのに大漁になったときに感謝する相手として機能していたのかもしれません。
海は魚介類などの恵みをもたらす場所であり、また溺れたり鮫などの危険にさらされるところでもあります。
海水浴場が整備されたりしてあまり現実的でなくなってしまった現在も、船乗りや海女さんの間ではある程度の信仰や迷信が息づいていることもあり、興味深いですね。

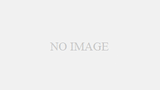
コメント