妖怪を種類別に見ると、大まかに人の形に近いものと、動物の形に近いもの、また目に見えないものがあります。
山の妖怪でもそれは同じですが、ほかの場所に現れる妖怪よりかたちが異様なものが多いと言えるでしょう。
山に現れる人型の妖怪でもっともポピュラーなものがテングだと思います。言わずもがな長い鼻や真っ赤な顔、高下駄を履いていたり、翼を生やしていることもあります。
ほかにも紀伊半島地方の妖怪でイッポンダタラというものがいます。一つ目・一本足で12月20日にだけ現れ、この日に山に入っている人を襲うと言われています。
動物が妖怪になったり、動物の形をした妖怪もいます。
特に山の中ではきれいな動物やかわいい動物に出会っただけで神秘的に感じますから、神の使いの白い蛇などの伝説が生まれたのも納得です。
目に見えない妖怪では、スネコスリやベトベトサンなどが有名かもしれません。
スネコスリは雨宿り中に足元にまとわりつく感じがするという妖怪で、目に見えません。
ベトベトサンも足音が後ろから付いてくる、足音だけの妖怪です。
目に見えない妖怪で、山を越えるときにみんながここで行き倒れてしまうという地縛霊のような存在ヒダルガミも目に見えません。
大体、難所が続くような場所で人に取り憑くということですから、科学的に言えば低血糖のことです。
ヒダルガミに憑き殺されないためには、何か少しでも食べるものを口に入れるといいということです。
こうして非常食をそこまでの道で食べきってしまったり、うっかり持ち忘れてしまうのを説話として防いでいたと考えられますね。

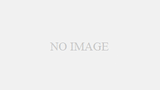
コメント