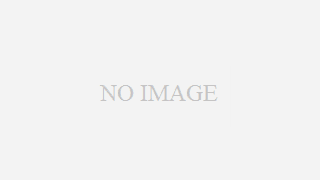 街の妖怪
街の妖怪 街の妖怪の怪談
現代妖怪である口裂け女や花子さんといったメジャーな怪談以外にも、古くから伝わっている街の妖怪の怪談はたくさんあります。例えばイヤヤという妖怪は追いかけてこない口裂け女のようなものですし、お寺の居住区に勝手に住み着いている古庫裏婆も花子さんの...
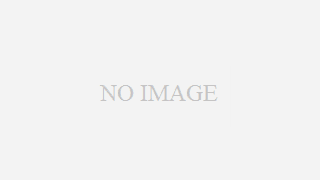 街の妖怪
街の妖怪 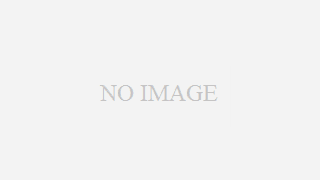 川の妖怪
川の妖怪 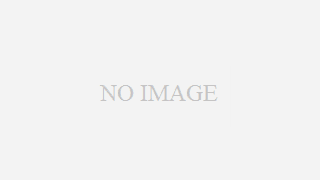 山の妖怪
山の妖怪 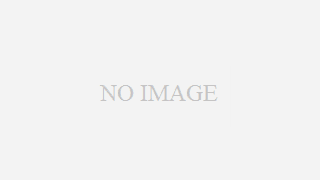 海の妖怪
海の妖怪 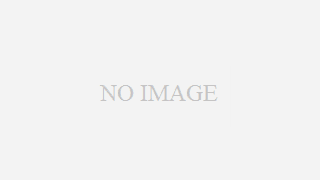 山の妖怪
山の妖怪 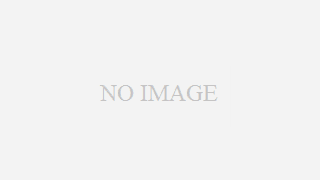 海の妖怪
海の妖怪 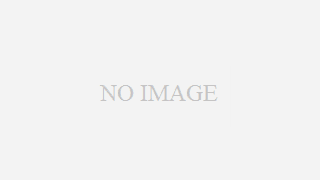 川の妖怪
川の妖怪 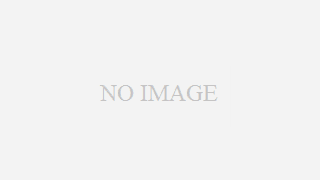 川の妖怪
川の妖怪 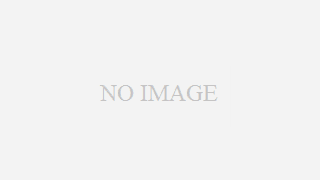 山の妖怪
山の妖怪 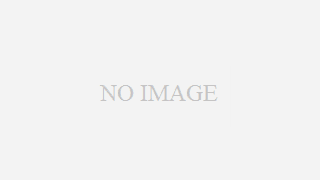 海の妖怪
海の妖怪 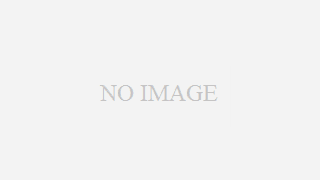 海の妖怪
海の妖怪 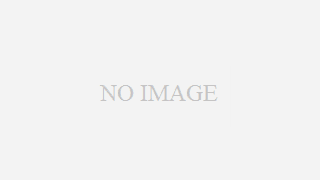 海の妖怪
海の妖怪